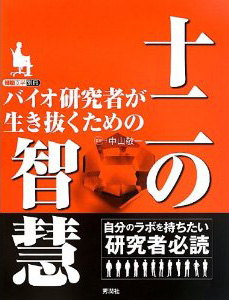医学部は崩壊する!? HTML (TEXT) 版

医学部は崩壊する!?
– 研修必修化がもたらす研究と教育の荒廃
HTML (TEXT) 版
臨床研修の必修化は、最近その功罪がしきりと論じられているが、その臨床医学に与える影響の最終的な評価にはもうしばらくの時間が必要であろう。
しかし、現在においてひとつだけはっきりしていることがある。それは研修必修化が基礎医学の分野に与えるダメージが、予想外に大きかったということだ。今、臨床研修の必修化によって、基礎医学に進む人材が激減している。こうした傾向がつづけば、日本発の臨床研究の実力は低下し、いずれは、医学界全体に大きなマイナス要因として影響を及ぼすことは必至である。
そこで今回の特集では、研修必修化によって基礎医学が被るダメージ、それが医療界全体にどう影響してくるのかを論じていただいた、九州大学生体防御医学研究所分子発現制御学分野教授/中山敬一氏の寄稿をお届けしたい。
はじめに
「今、医学部が最大の危機に瀕している」と言ったら、「何を大袈裟な」と、あなたは笑うだろうか?しかし、実際に日本の医学部では将来50年、100年にわたって禍根を残すような愚行がまさに今行われているのである。それは餓えた蛸がひもじさのあまり自分の足を食べてしまうような、将来のことをまったく考えない行為である。
数年前に始まった「研修必修化」は、診療面においてある程度の効用は認められるものの、基礎医学研究を直撃し、いずれは臨床医学研究も滅ぼすであろう。研究だけではない。このままでは、医学教育も次世代には崩壊すること必至である。そして、その先に待っているものは、教育も研究も低レベルの、大学という名の医療専門学校の出現に違いない。
小泉首相は「米百俵の精神」を掲げて国民の圧倒的な支持を得た。これはご存知のように、皆が困窮しているときに、あえて百俵の米を消費せずに将来の教育の糧に使おうという高邁な精神であり、最大の尊敬に値する姿勢であると思う。しかしながら、現在行われている医学部改革は、この精神とはまったくの反対の方向へ向かっている。私よりもよほど見識にすぐれた多くの医学者が同じ危機感を有しているにもかかわらず、誰もこの流れを止められない。そして、それ以上に深刻なのは、多くの医師や医学生が現在の危機に関する認識がないことである。
私はこのような問題を専門に研究する者ではないが、あまりの惨状に本業の合い間に筆を執ることにした。本稿では、現在の医学部が抱える病巣を摘出し、病理を調べ、治療方針を示したい。
1章
生命科学へと変貌を遂げた医学
かつての医学は
その大部分を経験に依存していた
我が国において、医学はもともと実学であった。一方で生命の構成原理を探求する生命科学は虚学であり、理学部に属していた。そして一時代前までは医学と生命科学はあまりにもかけ離れており、現実的に同一レベルで語れるような状況にはなかった。実際、20年前に私が受けた医学教育も、一部を除いて実につまらないものであった。
その理由は簡単で、ロジックがなかったからである。当然のことながら人間もひとつの生命体であり、その病気という異常状態には必ず原因があり、そしてそれを治す方法も理論のうえでは考えられるはずだ。しかし、私たちが受けた教育というのは、ほとんどの病気が原因不明、治療法はステロイド(作用機序は不明)という類いのものであり、ほとんどが経験にのみ基づいていた。現実的に理系学生の最高頭脳を集めている医学部で、なんのロジックもない暗記教育がなされていることは非常に悲しむべきことではあったが、当時の科学のレベルを考えれば仕方のないことではあった。
けれども明らかに時代は一変した。因果関係を明らかにすることによって成立する理論体系、つまり科学のひとつとしての医学が始まったのである。人間の体をひとつの生命体として捉え、それを分子レベル、細胞レベル、個体レベル、集団レベルで解析しようとする統合的な医学観が芽生え始めたのが20世紀終わりの大きな進歩だったことに、今にして気がつく。とにかく、現在では医学は立派なヒューマンライフサイエンスである。それは単なる学問上の話ではなく、すでに産業として、ヒトのメカニズムを理解し、それを応用することによって健やかなトータルライフを指向する時代が始まっている。
今までにない勢いを持って
進み出した医学研究
実際に私たちのまわりには、次第に基礎研究にもとづく成果が増え始めている。
EGF(上皮成長因子)レセプターはEGFに反応してタンパク質のチロシンをリン酸化するが、その研究から産まれたのが、EGFレセプターの阻害薬であるイレッサ。イレッサは今までほとんど打つ手のなかった、手術適応がない肺がん患者に対して明らかな効果を示す新規の抗がん剤であるが、一部の患者には致死的な副作用を有することが問題となっていた。しかし近年では、患者のEGFレセプター遺伝子の塩基配列の違いが薬剤感受性に関係あることが次第に明らかとなり、投与前に患者に対する有効性と副作用をある程度推定できるようになりつつある。これらは分子生物学や細胞生物学、さらにはゲノム医学による成果の結実と言うべきであろう。
同様の分子標的抗がん剤で有名なのはグリベックで、CML(慢性骨髄性白血病)に劇的な有効性があり、またプロテアソーム阻害薬のベルケイドはミエローマに著効を示す。さらに、ハーセプチンのような抗体医薬も登場し始めている。
そのほかにも、基礎研究の応用は意外に身近なところで現れている。よく思い出してほしい。ヒト型インスリンの大量生産が、いかに多くの糖尿病患者を救ったか。エリスロポエチン注射が、慢性貧血に悩む透析患者にとってどれだけ効果があったか。今まで抗がん剤による骨髄抑制で感染症を起こして亡くなっていた患者が、G-CSFのおかげでどのくらい助かったか。
医学が因果関係を探索し、解決しようとする姿勢を持つ真の学問になったのはつい最近のことである。とは言え、その後の発展のスピードには目を見張るものがある。21世紀になってヒトゲノム計画がほぼ完了し、私たちはその難解な設計図を一応は手にした。予想以上の難解さに手こずってはいるものの、それでもゲノム情報の取得は従来の科学の方法論を完全に逆にしたと言っても過言ではない。
今後は今までにない勢いと方法論を持って医学研究は進み、その果実は近い将来に臨床現場へ還元されることを誰もが夢見ていた。これからの生命科学、そしてその一分野であるはずの医学には、燦々たる未来が拓けてくるはずであったのだ。
2章
基礎医学を直撃した研修必修化
医学研究の将来に
立ちはだかった研修必修化
明るい未来が約束されたかに見えた医学の世界。しかし誰もが予想しなかった方向から災いはやってきた。研修医による医療事故の頻発やその背景にある研修医の過酷な労働環境に世論の批判が集中し、また大学の医局制度によるピラミッド型の支配構造を改革せねばならないという声が上がり始め臨床研修が必修化されたのだ。もちろん、そのような古い体質を改善する試み自体は悪いことではない。
研修の必修化によって、医学部を卒業して医師免許を取ってからも、さらに2年間(または3年間)の研修を受けなければ保険医登録ができない、つまり実質的に医師としての活動ができないという制度が始まった。これは言葉を変えれば、医学教育の実質的な8年化と捉えることができると思う。
現在のための医学と
将来のための医学
さて、ここで従来の医学研究の在り方について振り返ってみたい。医学は2つの側面を有する特異な学問である。つまり単なる興味のための学問ではなく、その学問から得られた最新の情報と技術を患者に還元していくことが求められ、研究と診療が車の両輪のように同時に進行しなければならない。別の見方をすれば、医学は現在のための医学と将来のための医学に分けて考えることもできるのだ。
現在の医学の基盤を支えているものは過去数十年にわたる基礎研究から得られた結果であるし、現在の研究は10年後、20年後の医学を支えるであろう。持続的な医学の発展を願うためには、常にそのエネルギーの一部を将来の投資にまわさなくてはならない。そうしなければ存続も発展もないことは、医学部に限らず、企業や国などどんな組織にも共通した自明の理であろう。特に研究開発という分野は既成の学問を超える創造の世界であるから、もっとも優秀な人材を配するべきであることは言うまでもない。
基礎医学講座を支えてきた
臨床医の大学院生
しかし実を言えば、以前から医学部は将来に対する投資にはあまり熱心ではなかった。6年にわたる医学部教育を終えて、そのまま研究をめざす者はほんの一握りというか、稀と表現したほうが正しい。1クラス100名の卒業生の中で、卒後すぐに研究をめざす者は多くて1?2名で、0名という医学部も少なくないのではないか。では、大学の講座の約半数は基礎医学なのに、これほど少ない人材でどのように研究を賄ってきたかというと、それは臨床医学からの供給に頼っていた面が大きい(図1)。
以前はかなりの数の臨床医が大学院生として基礎医学講座で研究を行った。その結果として基礎医学講座は優秀な人材を得て研究を遂行できたし、臨床医学講座は将来の臨床研究を行うための人材を養成できた。
彼らは基礎医学分野で研究のイロハを学び、世界をめざす姿勢を見て臨床へ帰り、臨床研究の担い手となった。また臨床からやって来た優秀な医者の中には、日常のルーチンワークに追われる診療業務よりも学問として探究心をそそられる医学研究に転向する者も少なからずいて、卒後すぐに基礎研究をめざすストレート組と臨床からの転向組が、以前は医学部の基礎研究と教育を支えていたのである。
研修医の大学離れの
しわ寄せが、基礎医学講座に
そうしたバランスを崩したのが臨床研修の必修化なのだ。研修必修化は当初は基礎医学講座に関係のない、単なる臨床研修制度の変更程度に受け止められ、基礎医学講座では誰もそれを真剣に危惧する者はいなかった。しかし蓋を開けてみれば、多くの研修医は症例の豊富な大学外の市中病院での研修を希望し、大学からは若手が姿を消して、臨床講座ですら深刻な労働力不足に陥り、そのツケは末端である基礎講座に押し寄せ、基礎講座には大学院生は来なくなった(図1)。貧すれば窮し、窮すれば鈍す。医学部全体として研究や教育が大切なのはわかっていても、目の前の人材不足はいかんともし難い状況になったのである。
たとえば、現在までの9年間に私の研究室に入学した大学院生は30名いるが、そのうち医学部出身者は15名で、卒業後すぐに研究を始めるストレート組の学生が6名、臨床から来た大学院生は9名であった。残りの15名はその他の学部からで、その内訳は理学部6名、薬学部5名、農学部4名であった。
毎年数名の新入生のうち、おおよそ半数は医学部出身者だったのが、研修必修化が始まってから2年間はひとりも医学部から大学院生が来ない状況がつづいている。この流れは今後もつづくものと予想され、私の所属する研究所では医学部以外からの人材募集を積極的に行うことにした。このような傾向は、全国どこの大学の基礎医学講座でも似たようなものだと思われる。
3章
研究の凋落そして教育の崩壊がやってくる
将来への投資を怠れば
研究能力の低落は必定
現在のような状態がつづけばどうなるだろうか。事実上日本の理系頭脳のトップを占めている医学部から、もっとも創造性の要求される基礎研究にまったく人材が行かなくなるという可能性が出てくる。畢竟、基礎部門における人材の数と質の低下は避けられず、当然研究能力も低落するであろう。
すなわち、未来の医療の基盤となる新しい知見を生み出すことを自ら放棄する道を選んでいるのにほかならない。将来への投資を怠った組織がたどる運命がどのようなものであるかは歴史が証明しているとおりである。
基礎医学部門の凋落は
実は医学部崩壊の序章
基礎医学部門の凋落は、実は医学部崩壊の序章にすぎない。臨床部門においてもその影響はかなり早期に現れるだろう。基礎部門で優秀な医師を学ばせることができないばかりか、大学院生という名のもとに診療行為の下働きをさせてきたツケがある。早晩、臨床研究能力の低下はやってくるはずだ。実験のイロハをまったく知らない多忙な医師にどのような研究ができると言うのか。
今まで彼らが基礎研究で学んでいたものは、決して実験手法とかテクニックといったものだけではない。研究の意義、研究に対する姿勢、立案と遂行に対する種々の知恵、世界最先端への距離感、等々、科学としての医学を肌で実感することがその最大の恩恵だったのだ。そのような訓練を受けていない人間が臨床研究の担い手になるのである。あっというまに日本の臨床研究能力は低下するだろう。
大学における研究能力の低下が国民の健康維持にとって直接的な損失であることは言うまでもないが、間接的にも医療バイオ関係をすべて海外に独占されることは経済的に巨大な損失であることは明らかである。
そもそも大学病院の存在意義は、なんだったのか。患者は何を求め、そこで働く医師は何を指向していたのか。現在、それがまったく曖昧になってしまったために若い医師たちが大学を離れていくのではないか。
大学病院が市中病院と異なる点は、大学が最先端の医学を研究し、その成果をいのいちばんに患者への診療に応用するというその一点に尽きるだろう。その大学病院が研究行為を放棄してしまえば、なんら市中病院と変わるところはないばかりか、今まで長らく白い巨塔状態であった大学に勝ち目はないことは火を見るより明らかである。医師にとっても、そのような大学病院にはなんの魅力もないに違いない。
予想されるもっと深刻な事態
それは、医学教育の崩壊
そして、実は研究における打撃とはくらべ物にならないほど深刻な事態が予想される。それは医学教育の崩壊である。研究の低迷は、適切な改革をすれば5年、10年で取り戻すことが可能である。しかし教育の崩壊は50年、あるいは100年の損失になりかねない。このまま現在の状況がつづけば、基礎医学研究の世界から医学部出身者は払底する。当然、非医学部出身者が医学部の基礎講座の教官ポストを埋めることになるだろう。つまり医学教育を受けたことのない人たちによって医学教育が行われるようになる。
誤解のないように付け加えるのだが、私は医学部の教官をすべて医学部出身者にせよと言っているわけではない。分野によっては非医学系の研究者のほうが優秀な場合も多いし、それらの研究者が医学部に入ってくることを排除すべきではない。実際、私の所属する研究所も医学研究所と銘打ってあるが、基礎部門の半数は医学部出身ではない。しかし医学教育を受けたことのない教官だけが明日の医学を担う若者の教育を行うことに対しては、以下の理由によって反対である。
医学部で受ける教育というのは並大抵のものではない。まず解剖学(=正常構造)や生理学(=正常機能)を習い、その異常としての病理学(=異常構造)や臨床医学(=異常機能)を習う。つまり人間というひとつの生物に関して、構造・機能についての正常・異常をありとあらゆる角度から6年間にわたって徹底的に叩き込まれる。その結果、人間という生物に対して「個体レベルでの理解」が感覚的に芽生えてくる。これは他学部の人には絶対にない感覚で、それを独学で学ぶことはまず不可能であるし、私は医学部を出ていないのにこの感覚を身につけている人に出会ったことがない。
それは医学部6年間で得る知識の量が膨大なだけでなく、実際に解剖を行ったり、患者を診察したりしなければわかならないことばかりだからである。医学教育は6年かかり、他学部にくらべれば2年のまわり道ではあるが、この「人間個体レベルの理解」は、ライフサイエンスを行っていくうえで絶大な力を発揮する。それは当然医学教育に対しても同様である。私自身は以前医学部に行ったことを非常に後悔した時期もあったが、今ではそんなことはまったく思わない。
いくら分子や細胞や動物のエキスパートであろうと、人間個体への最終的な理解に乏しい教官が教える医学は、自ずとその説得力に限界があろう。今ですら医学生は基礎医学の授業は単なる試験のために受けていて、決して自分の医師としての素養に役立つとは考えていない風潮が強いが、人間個体と切り離された教育が進めば、ますます基礎医学への興味は失われ、結局のところ医学部は、生命の構成原理すら理解していない医療技術者の養成機関となり果てることは目に見えている。
くどいようだが、もう一度誤解のないように付け加えておくと、私は基礎医学部門の教官をすべて医学部出身者で独占せよ、などという偏狭な意見を述べているのではない。中途半端な科学しかできない医学部出身者よりは、世界的なレベルの研究をしている非医学部出身者のほうがよほど迫力のある講義ができるだろうし、学生に訴える力も強いだろう。
私が声を大にして言いたいのは、そのような世界レベルの研究を行える人材を医学部から豊富に供給できる体制を整えよ、ということである。もともとそれだけの頭脳持った人材を医学部は抱え込んでいるのである。自分の学部の基礎教育を自分の学部出身者で賄えないことほど情けないことはない。
4章
改革案:大学の役割の明確化と医師の二分化
単に昔に戻すのではなく
現方式のさらなる改良を
では、研究の凋落、教育の崩壊を招かないためにはどうすれば良いのだろうか。研修必修化を止め、医師の技能向上と医局人事からの脱却をめざしたはずの現方式を旧に復すれば良いのか。私はそうは思わない。
現方式は長期的な視点に立てば前記のごとく、著しく瑕疵のある方策ではあるが、少なくとも目先の問題に対してはある程度有効であろうから、単に昔に戻すのではなく、現方式をさらに改良すれば良いのではないだろうか。具体的な案としてはまだはなはだ荒削りだが、私の案を紹介したい(図2)。
大学病院を完全に
リサーチホスピタル化すべし
まずこの問題は大学病院の存立基盤に端緒を発していることを考えれば、大学病院自体をいかに変えていくか、市中病院といかに差別化を図っていくか、が第一の改革となろう。過去において大学病院はブランドであった。単なる風邪の患者すら大挙して押しかけ、3時間待ちの3分診療と言われた時代があった。しかし、もはやそのような時代ではない。患者にも若手医師にも見放され始めている。
先にも述べたように、大学病院の最大にして唯一のアドバンテージはその研究開発能力にある。それを踏まえれば、大学病院は完全なリサーチホスピタル化をしなくては社会的な使命を果たせないであろう。基礎研究の成果を踏まえたtranslational medicineを徹底的に行わなくては、もはや大学病院の価値はない。最新の治療法、最先端の治療機器、最高のスタッフがそろっている病院でなくてはならず、従来のような人事権だけで他の病院を支配下に置くようなことでは誰の支持も得られない。患者にとっても医師にとっても真のプレステージでなくては意味がないのだ。
市中病院で行えることは市中病院に任せておけば良い。もはや大学病院には通常の外来は必要ないだろう。大学病院には、完全紹介制で実験的医療のインフォームド・コンセントが得られた患者のみ受け入れ、綿密なプロトコールのもとに、きちんとした計画と科学的評価を行う体制が何より必要である。
大学病院に勤務する医師については、その指導層は固定せざるをえないにせよ、中堅以下は市中病院との循環を保つ制度をつくるべきだろう。そして、指導層に対してはプレステージを与える意味で報酬と肩書きを別格にする必要もある。全国の大学病院における指導層の人数などたかが知れているし、その報酬を少々上げることで医学研究と教育の改革ができるならむしろ安いものだ。
大学院のシステムを
抜本的に見直す必要
大学病院の根幹が研究を基盤とした最先端医療にあるとするならば、その指導層は当然医学研究に対する造詣が深くなければならない。そうなるためには現在の大学院のシステムを抜本的に見直す必要がある。
現在は「医学博士」のプレステージは見る見る低落し、むしろ「専門医」の肩書きを欲する医師が増えている。つまり大学院で学ぶことの魅力もメリットも感じられなくなってきているのだ。
その元凶は、1990年代後半から始まった大学院大学化にあると言っても過言ではないだろう。これ以降、医学の進歩を担うべき基幹大学がこぞって大学院大学となり、本来の必要性をはるかに超えた学生定員を抱えることになった。数の充足を図るべく、質を犠牲にして量を水増しするという愚挙に出たのだ。結果的に起こったことは、多くが大学院に入学するものの、きちんとした研究や教育が行われないために、評価もいい加減な“なんちゃんって医学博士”の大量生産である。学位はプレステージではなくなり、持っていてもなんのメリットもない称号になり下がった。そもそも、博士号を持つ人間を倍増させて社会にどういうメリットがあるのか、理解に苦しむのは私だけではあるまい。
今後は大学院の質の再建をめざすべきである。現在の大学院の実情は誰が見ても以前よりも圧倒的に悪化している。少なくとも医学系大学院に対しては、定員充足率に関して文部科学省は寛容であるべきだ。量よりも質の充実こそが現在の喫緊の課題であるからである。
博士号か、専門医か
2つの道を明確に示す
大学院で真の研究を学ぶことを目的とする者だけが入学し、厳格な審査を経て学位を授与する少数精鋭主義にあらためるべきである。このような資格を有する者が大学病院における指導層を形成するようになれば、必然的に研究志向の強い若手医師は、大学院に入って基礎研究の門を叩くことにメリットを感じるようになるだろう。
このようなサイクルが定着すれば、将来の医学の発展に貢献しようと志す人たちは、その人生の少なくとも4年間は腰を落ち着けて研究するという経験を積めるだろうし、それは基礎研究部門を活性化し、さらには臨床研究部門の成果を増し、真のtranslational medicineへの貢献となり、最終的には国民の利益となる。
すべての医師が平等でひとつの道を歩む時代はすでに去った。これからは将来の投資のために医学を志す医師と、現在の医療技術を駆使して患者の治療にあたる医師が、それぞれの志向と適性に応じてその役割を分担すべきであり、当然大学病院と市中病院もその目的と役割を明確に分離すべきであると思う。つまり大学院に入学して博士号を取ることをめざす道と、市中病院において専門医をめざす道という2つの道の存在を医学生に明確に示し、選択させることを促す方策が何より必要である。繰り返すが、全員が平等でなくてはならないという時代ではもはやないのだ。
今、もっとも大切なのは、医学部が存亡の危機に立たされていて、早急な対応が必要であることをひとりでも多くの方に認識していただくことである。すべてが手遅れにならないうちに、適切な制度の改革がなされることを切に希望したい。

教えて、先生! HTML (TEXT) 版
他人と違う生き方
僕の生き方はね、他人とは全く違うんだ。国立大の医学部を卒業後、臨床研修をせずにすぐに基礎研究の道に進んだんだ。国立大を卒業して私大の大学院に行く人はほとんどいないと思うけど、僕の場合は順天堂大学に良い先生がいたから、そこの大学院に行くことにした。
大学院を出てからは理化学研究所に入って、そのあとすぐワシントン大学に留学し、約5年間過ごした。アメリカは32歳くらいになったら独立するのが普通だけど、当時32歳だった僕は日本に帰っても独立できないし、そもそも日本に帰るつもりはなかったんだ。
ところがボスが、何を思ったか日本の製薬会社の研究所所長になっちゃったのさ。「お前も日本に来い、そこで独立させてやるから」って言うから、じゃあそうしようかなと思って……意外な形で帰国した。日本では医学部卒は普通製薬会社に行かないし、研究やりたいのに企業行くヤツもまずいないけどね。 でもボスが語ったのは、日本トップの若手研究者15人を集めて新しい研究所を作るっていう、とても夢のある話で、それに惹かれたんだよね。今となっては詐欺にあったような気もするけど(笑)。
製薬企業に勤めて、初めの1年はハッピーだった。何をやってもよかったからね。でも、次第に研究の方向性が狭められてしまった。ラボを持たせてもらえたのは計画通りだったけど、研究者15人も結局集まらなかったしね。ともかく、わずか1年で企業の方針が変わったのは誤算だった。 実はそのちょっと前から九大に来てくれないかって誘われていたんだけど、はじめは断っていた。でも最終的に九大に行くことを決意したのは、大学は研究の自由が保証されているから。とにかく他人とは全く違った経路を辿って、九大の教授になった。当時まだ34歳だった。

<プロフィール>
中山敬一(なかやま・けいいち)主幹教授
1986年、東京医科歯科大学医学部卒業。順天堂大学大学院修了後、政府系研究所、米国留学や企業経験を経て1996年九州大学・生体防御医学研究所教授。2009年より同主幹教授。2010年夏、著書『君たちに伝えたい3つのこと―仕事と人生について 科学者からのメッセージ』を出版。現在、重版や韓国からの出版オファーなどの反響を呼んでいる。
「過激すぎる」著書の出版まで
九大に来てまず行ったことは学生を集めることだった。そのために当時はまだ珍しかったウェブサイトを作って、そこに学生をアジる(焚きつける)ような文章を載せた。 きっとやる気のある学生なら食いついてくると思って、エサを撒いたんだ。案の定、このウェブサイトは多くの研究者の間で結構評判になった。だってホンネがそのまま書いてあるからね。 ところが釣れたのは学生だけではなかった。ある日科学専門誌の出版社から原稿の依頼が来たんだ。そこでウェブの内容をかなり穏やかな表現に変えて原稿を書いたんだけど、編集長から「過激すぎる」ってストップがかかって、ボツになっちゃった。 科学専門誌は研究者とか医者が読者だから、医者に喧嘩売るようなマネは困るわけだよね。仕方ないので、書いた原稿をそのまま全部ネットにあげたら、今度は『もしドラ』を出している超メジャーな出版社からオファーが来た。 まさに捨てる神あれば拾う神あり、というか人間万事塞翁が馬、というか。いやむしろ藁しべ長者的な展開かな。
著書への反応
この本では当たり前のことを書いたつもりなんだけど、キャッチコピーとして「過激すぎる」という帯付きで出版された。ネットでは「正論」という意見と、「トンデモない」という評価に二分されているみたいだね。 よくあるのは「面白かったけど、最後で引きました」っていう反応。何でかっていうと、最後の部分に、女性が科学者になるために「結婚は△、出産は×」って書いちゃったんだ。僕は基本的に、科学には男性も女性も関係ないと思ってる。 今の風潮は女性にとって追い風になっていて、それ自体は悪い事じゃないと思うんだけど、でも子どもを育てながら世界一流の科学をやるのはとてもできないと思う。マラソンやるときに、子ども背負って走る人はいないでしょ?
世の中には、真実なのに口にしてはいけないことがたくさんある。でも自分が人生を選ぶときに、1つくらい参考にできるホンネの本があってもいいんじゃないのって思うわけ。逆にそういうホンネを書かないと、この本の価値はないわけさ。綺麗事に騙されて自分の一生決めて、あとでつまんなかったなって思ったら嫌でしょ?
著書への反応
学生へのメッセージは非常に単純明快で、「面白い人生を送ろう」ってことだけさ。僕の生き方は他人とは全然違うけど、もちろん戦略があってその道を選んだわけ。 僕の中では、研究は医者をするより圧倒的に面白い。医者の仕事は毎日同じことの繰り返しで、知的興奮がないんだよね。しかも冒険ができない。新しいことがない人生はつまらないよ。でも大部分の人にとって、他人と違う道を選ぶことは怖い。
今の世の中は、理系で一番頭がいい人は医学部行っちゃうでしょ。でも医者やるにはそんなに高度な頭脳はいらないんだよ。出来る子はやっぱり数学とか物理とか、一番頭脳が必要なところに行ってほしいね。医学部に来た子の中で、1割でもいいから、自分の才能を使って面白い研究をしてほしい。 面白いというのは、人がやったことないことをして、毎日が驚きや発見に満ちていて興奮できる人生。研究者という、一番面白い、一番自由で、一番興奮するような職業になんでみんななりたがらないのか、理解しかねるね。今の若い人は目先の安定を求めてリスクをとりたがらない。でもリスクをとらなかったらリターンもないわけさ。
頭を使って、自分なりの戦略で、自分の進路を決めてほしい。詳しくは、著書を読んでください(笑)。人生1回しかないからね。研究者は面白いしエキサイティングだけど、ある意味世界との競争だから疲れるんだよね。休んでいられないし、こんな人生は1回でいい(笑)。けど人生は1回しかないから、一番面白いと思うことをやっているのさ。

教授からのメッセージ

「よくある質問」編
No. 1 基礎配置について
1. 九大医学部の使命
私のような他大学から来た者の目から見ると、九大医学部の教育プログラムは大変独創的で素晴らしいプログラムであると常々感じております。その教育担当者による情熱溢れた企画力には陰ながら感服しておりました。
但し、これはあくまでも方法論の話であって、医学教育の本質的なこととなると九大ほど愚かな教育をしているところも珍しいのではないかと思います。と申しますのは、現在の九大医学部の教育は「医療者養成学校」のそれに堕しているからです。
医学は基礎理論探求と応用学問(=臨床)という2つの側面を持っており、当然前者は未来の医学の基礎となるべく、10~20年後の医学を模索して行われるもので、逆に後者は現在苦しんでいる人々に対して今までの知識の蓄積を基に医療サービスを施すのがその役目です。つまり基礎研究は「未来のための医学」、臨床は「現在のための医学」です。では旧帝国大学であり、大学院重点化を受けている九大医学部としては、基礎研究と応用開発のどちらがより社会からの要請が大きいのでしょうか?
それは基礎研究だと私は考えます。何故なら応用開発(=臨床)は臨床医養成に重点を置いたF私大やK私大でもできるからです。私はA国立大学を卒業して、その後B私立大学で臨床研修を受けました。そのとき実感したのは、B私大の方が、A国大よりもはるかにレベルの高い医療サービスを施していたということです。これは私にとって非常な驚きでした。確かに頭脳のレベルはA国大の方が勝っていることは事実でしたが、実際の臨床というものはそれだけじゃないんだということがわかりました。もちろん九大の頭のいい医者でも十分にいい臨床をできると思いますが、それは松井選手にサッカーをやらせたり、中田選手に野球をさせたりするようなものです。はたから見ていて非常にもったいないでしょう?つまり私の言いたいことは、九大卒業生は、それなりの頭脳を持った人でなくてはできない、独創的で未来を拓く原動力となるような基礎研究の道を歩むべきだと信じています。理想的には上位20~30%の学生は基礎医学研究を目指すべきです。
しかしながら現状はいかがでしょうか?全卒業生の中で基礎研究者を目指す人はほぼゼロに近いというお寒い状態です。
2. 基礎配置の意義
それでは基礎配置の持つ意義とは何でしょうか?それは基礎医学研究の「真の」面白さを学生に教えてあげることです。「真の」と言ったのは、研究の面白さは未知の真理の解明という、人間だけに与えられた最も高尚な特権 – 知的好奇心 – を刺激することにあるからです。授業は過去の知識の集大成を系統的に教えるだけですから、どうしても「真の」面白さは伝わりません。それは臨床も同じでベッドサイドでの体験がなければ、講義を聞いても眠いだけでしょう。基礎配置は基礎医学研究室に与えられた貴重な「体験」のための時間であり、本格的な医学研究者を輩出するためには是非とも必要なプログラムです。
3. 基礎医学研究者を目指す学生が少ない原因
可能性のある原因は2つ考えられます。1つは九大医学部学生自体の資質によるもの。もう1つは九大医学部の教育プログラムによるもの。答えは明らかに後者です。何故ならば当研究室における過去2年の基礎配置経験がそれを物語っています。
当研究室は「医学部学生は頭が良く、本当に真剣にサイエンスの面白さを教えてあげればきっと興味を持つだろう」という信念のもとに基礎配置に取り組んできました。初年度は不幸なことにその姿勢が学生に知られていなかったために、全員がやる気満々というわけではありませんでしたが、そのうち3人は非常に興味を示し、2人は卒業後すぐに当研究室に大学院生として入学しました。次年度は前年度の失敗を教訓にして、初めから学生に我々の姿勢を明確に打ち出しました。曰く、1ヶ月ではサイエンスの面白さも何もわからないので、最低2ヶ月(できればそれ以上)続けて来られる学生だけを対象に、本格的な研究体験をさせる、というメッセージです。それでも4人の枠の中に6人近くの応募があったように聞いています(学生から聞いた話なので正確ではないかも知れません)。
この4名はさすがに覚悟してきただけあって、非常によくやってくれました。端から見ても研究を楽しんでいる様子がありありとわかりました。しかし結論から言えば、最終的には誰も卒業後すぐに来るという人は残念ながら皆無でした。何故でしょうか?初年度と次年度と何が違っていたのでしょうか?4人の学生ともほとんど同じだったコメントがそれを物語っています。「もう1、2年早く基礎配置があったら、きっと自分は基礎研究の道を志していたと思う」。つまり初年度は5年の6月に基礎配置があったのに対し、次年度は6年の4~5月になった、このたった1年の違いだけです。
医学部6年生となるとすでに時間的・精神的に余裕のない状態になっています。そのような切羽詰まった状態の学生に、将来の進路を180度転換するような選択をさせるのは非常に酷なことですし、もう固まりつつある心を溶融させるのはそう簡単なことではありません。まさに「鉄は熱いうちに打て」です。冷めて固まった鉄を曲げることは、もう難しいのです。これは、理屈ではないのです。
では基礎配置の時期を単に前にずらせばいいかというと答えは否です。一昨年まではそういうプログラムで基礎配置を行っていたにもかかわらず、ほとんど基礎研究者を目指すような学生が輩出しなかったではないか、という反論があるでしょう。これは残念ながら基礎研究室側にも情熱の欠如という大きな問題があったからだと思います。しかしながらこの問題に関しては、取り組み方を変えるように努力することは可能です。まず、何故基礎配置に対して真剣に取り組まないかという原因に対して、それを究明する必要があります。
4. 現在の基礎臨床研究室配属について
現在の基礎「臨床」研究室配属は上に述べたような基礎配置の本質から大きくはずれています。まず第一に臨床研究というのは学生が学ぶべき研究とは異なるということです。臨床研究は応用研究であり、基礎理論があってそれを目の前の患者にどうフィードバックしていくかという研究です。それはそれで必要なものですが、それは医者になって問題意識が芽生えてから学べばいいことです。それよりも頭の柔らかい学生のうちに本格的なサイエンスを見せておく方が、将来臨床に行って研究をするときもきっと役に立つでしょう。「まず本質を見せてから、応用を学ぶ」というのが正しい姿勢であると思います。
現行の基礎臨床研究室配属は単に臨床教室の「勧誘」の場になっている、との指摘があります。それは受け入れ学生数の数を見てもわかります。臨床での研究で20人もとるところがありますが、一体どんな研究をやらせるのでしょうか?実際は単に研修医の前倒しに過ぎないのではないかという声さえあります。とにかく本来の基礎配置の目的であった「学生に本当の科学研究の面白さを教える」という趣旨から完全に逸脱していることは確かです。
5. 問題点のまとめ
- 九大医学部の卒業生はほとんどが医療者となっており、医学者になっていない。
- 九大医学部に求められているのは、医療者ではなく、医学者の養成である。
- 基礎配置は本格的な医学研究者の輩出のために是非とも必要である。
- 学生に問題があるのではなく、プログラムの時期に問題がある。
- 基礎研究室の取り組み方にも問題がある。
- 現行の基礎臨床研究室配属は、本来の基礎配置の意義とは全く異なるものとして運営されている。
6. 改革案
- 基礎配置の時期を現行の6年生から4~5年次に行うようにする。できれば6、7月で興味がある学生に対しては8月も対象にする。
- 臨床への配属は止める。
- 基礎研究室が真剣に取り組むよう、ガイドラインの設定等の積極的な施策が必要である。
- 興味を持った学生がその後も研究との接点が持てるように工夫すべきである。
7. 当研究室の現在の取り組み
残念ながら現行の基礎臨床研究室配属はその本来の目的に対して有効に機能しないことが判明したので、当研究室では医学部の改革を待つことなく、独自で以下の3点について試みを始めています。
- 「分子生物学勉強会」というゼミの開催。毎年5~7月の毎木曜日に読書会をしています。単なる読書会ではなく、物事を考えさせるような工夫をしています。
- 「サマースチューデント」制度。学年を問わず、夏休みを利用して希望する学生を受け入れて研究させています。基本的には分子生物学勉強会の後にそのまま参加する学生が多いです。但し、ほとんど2週間くらいしか学生の都合がつかないところが欠点です。
- 「分子生物学研会」制度。サマースチューデントに来た学生達が作った会で、夏休み後も研究室に出入りして実験を続けています。
No. 2 よくある質問1 – 私には研究者としての資質があるのでしょうか?
1. 研究者の資質は論理性である
皆さん、研究者というもののイメージとして、「誰にも考えつかないような突飛なアイデアをどんどん思いつく」エジソンやアインシュタインみたいな人を想像していませんか???基礎研究はしてみたいけど、自分にはそんな能力が果たしてあるのだろうか、と不安に思っている人もいるのではないですか???実はこの類の質問は、私のところへ切羽詰まった表情をして来る学生さんから聞く質問の中で最も多いものなのです。
生命科学者に求められる第一の資質は、意外に思われるかも知れませんが、「論理性」なのです。つまり、突飛なアイデアではなくて、A→B、B→CならばA→Cというような、確実で緻密な思考能力が要求されます。そして、君達九大医学部生のほとんどは、求められるレベルを既にクリアしています。だから、君達は生命科学者として、きっとある程度までは問題なく進めるでしょう。しかし、世界レベルの科学者になれるかどうかは、プラスαが求められることはいうまでもありません。それは「努力」であったり、「才能」であったり、「運」であったりします。
2. 君達は既に開幕一軍入りだ
野球選手をイメージして下さい。全員がイチローのようなスーパースターになれるわけではありません。それはどんな職業でも同じです。九大医学部に入学できるだけの頭脳を持った君達は、既に開幕一軍入り程度の実力を兼ね備えています。しかしレギュラーになれるかどうか、エースピッチャーになれるかどうか、4番バッターになれるかどうかは、その人次第です。私が言いたいのは、君達ならばきっとある程度以上のレベルまでは到達できる、少なくとも食うには困らない生活はできる、(だろう)ということです。
3. スーパースターを目指すためには一流のラボへ行け
全ての職業はそうですが、誰でも努力すればスーパースターになれるわけではありません。残念ながら、医学研究者にとっての「素質」を明確に規定することはできません。しかし、その必要条件は明らかです。それは大学院生時代を過ごすラボは、一流のラボに行け、ということです。
大学院生のときの教育がその人の科学者としての基盤を形成することは明らかです。また一流のラボに行けばそれだけ一流の研究をできる可能性があり、科学者としての業績を積むことができ、さらに次のステップ(ポストドクトラルフェロー)で一流の研究室へ進むことができます。大学院生のときの業績はラボの実力に依存する部分が多いので、いかに君達が優秀でも、もし二流・三流のラボに行ったら業績は出ず、いいところへポスドクも行けず、結局いいポストにも就けない、というmalignant cycleに入る危険性が大です。
4. 老舗は止めて、キャピタル・ゲインを狙おう
上で、一流のラボに行け、と言いましたが、一流の中にも「これからもっともっと伸びていきそうな一流」と「既にプラトーに達している一流」があります。世間で言う超有名研究室(いわゆる老舗)は後者がほとんどです。既にプラトーに達している研究室の多くは、ものすごい数の学生がいて、教授はほとんど研究室にはおらず、一握りの学生以外は、ほとんど討ち死に状態にある研究室もあります。
株を買うと、業績に応じて配当がもらえます。これをインカム・ゲインといいます。しかし株は、それ自体の価格が変動しますから、会社の規模が拡張する時期に株を買えば、株自体の価格が大きく値上がりすることになります。つまり安いときに買って、高いときに売る、この差額による儲けをキャピタル・ゲインと言います。「既にプラトーに達している一流」は既に十分株価が高いですから、インカム・ゲインしか狙えませんが、「これからもっともっと伸びていきそうな一流」では大きなキャピタル・ゲインが期待できます。サイエンスの世界も同じで、皆さんも研究室を選ぶときには「これからもっともっと伸びていきそうな一流」の研究室を目指すべきだと思います。
具体的に言うと、教授がまだ若くて、ここ2~3年で業績が急速に伸びているところがお勧めです。後は土日や深夜にどれだけ研究者が実験しているか、もいい指標となります。土日・深夜に電気が消えているラボにいいラボはありません。研究室のミーティングや抄読会に参加させてもらうのもいいアイデアです。どのくらい真剣に科学に取り組んでいるかがわかります。では実際にどのような研究室があるのか、というリストをここに掲載するのは、ちょっと問題があるので、個人的に私の部屋まで相談に来て下さい。事前に電話をもらえれば、必ず時間を作ります。
No. 3 よくある質問2 – 臨床を2~3年してから基礎研究したいのですが?
1. 気持ちはよくわかりますが、それは最低の選択です
折角医学部に入って、6年も勉強してやっと医師免許を手に入れたのに、全く臨床経験をせずに基礎研究に打ち込んでいいものかどうか。自分にとってまだ臨床がいいのか研究がいいのか迷いがある。とりあえず2~3年研修医をしてから、基礎研究の世界に行くかどうか考えてみたい。と、相談に来る人が毎年必ず数人います。気持ちはよくわかります。実は私もそのようなことを言っていた一人ですから(下記参照)。しかし、結果から申せば、それは最も愚かな選択なのです。
2. 多田先生の一言で
私の経験から話しましょう。私は医学部4年生(M2)のときに、当時東京医科歯科大学の教授であられた笹月 健彦先生(現九州大学生体防御医学研究所・教授)の講義に感銘を受け、夏休みや春休みを利用して研究室に出入りし、細胞免疫学の実験をさせて頂きました。この体験を通じて、免疫学者の道を歩もうと心に決めたわけですが、実は私も「2~4年間臨床をしてから、基礎に行こう」と考えていました。そんなとき笹月先生が九大に移られることが決まり、大変ショックを受け、東京の別の大学の免疫学研究室を探しました(実はその頃、九州は地の果てだと思っていた私には、九大に行くというオプションは夢にも思なかったのですが、今は東京の大学から学生が来ないと言って怒っています)。当時、東大には多田 富雄先生という免疫学の大御所がいて、一度多田先生に面接して頂いたことがあります。その時に、「2~4年臨床をしてから基礎に行きたい」とのたまわったところ、「こんなにサイエンスの世界が革新的に進歩しているのに、2年も無駄にしてどうするんだ」と叱られました。今から15年前の話です。もちろん現在の方が15年前と比較にならないくらい、凄いスピードでサイエンスは進歩しているのです。
3. 5年の遅れは取り戻せない
科学者に出身学部の壁はありません。いったん科学者を目指した瞬間から、君達のライバルは医学部出身者だけではなく、理・薬・農・工学部出身者との競争になります。しかし彼らの卒業は22歳で、大学4年生で研究室に配属されるところも多いので、実質21歳で研究の道に入ることになります。それに対して医学部教育は6年間あり、どんなに早くとも卒業は24歳です。君達が卒後すぐに研究を始めるとしても、すでに3年のハンデがあるのです。そのハンデは決して挽回不可能なものではありませんが、かなり大きいことは事実です。なのに「とりあえず2~3年研修医をしてから、基礎研究にいくかどうか」なんて迷っているのは、全く馬鹿げています。5年も遅れてしまったら、もう取り返しがつきません。だって君が大学院に入学するときに、相手はもう大学院を卒業してポスドクをしているのですよ。
私の大学院のときにS君という理学部出身の同級生がいました。当時、私とS君の上司の先生は中内 啓光先生(現筑波大医学部免疫学講座・教授)でしたが、中内先生曰く、「中山君、既に3年のハンデがあるからすぐに追い付けとは言わないが、5年後にS君に追いついていなければ科学者としてはダメだよ」と言われました。ちなみにS君は大学院生のときに独力でNature誌に論文を出したスタースチューデントでした。つまりそのS君が8年かけていくところを5年で行けというわけです。それだけでも厳しいのに、さらに2~3年も遊んでいたら、と思うと今でもぞっとします。多田先生に叱られたお陰で、最低の選択をせずにすみました。
4. なぜ迷うのか - 結論の先送りは止めよ
では、なぜ「とりあえず2~3年研修医をしてから、基礎研究に行きたい」と言う人が多いのでしょうか?これにはいくつかの理由が考えられます。例えば、折角医師免許を取ったのだから医者をしてみたい、将来の収入が不安なので手に職を付けておきたい、親の希望、等々。しかし真剣に人生を考えている人ならば、これらの理由が、上述した「5年の遅れ」を正当化するだけの説得力を持っていないことに気付く筈です。
経験として医者をしてみたいという気持ちはわかりますが、それは君達がたまたま医師免許を持っているだけのことであって、その他にも経験としてやってみたいことはいくらでもあるはずです。例えば絵描きになってみたい、モデルになってみたい、八百屋になってみたい・・・きりがありません。自動車免許を持っているからといって、タクシードライバーになってみたいと思いますか(註:タクシードライバーには2種免許が必要)。将来の収入が不安というのも、チャレンジする前から保険を掛けておこうとするのはよくありません。保険を掛けて本業を疎かにするのは本末転倒です。親の希望・・・誰のための人生ですか?君の人生の岐路の中でも最も大きい決断を迫られているときくらい、自分の意志で決めなさい。
「2~3年臨床をしてから基礎に行きたい」という学生さんから、私が感じる最も大きい要素は、「今すぐ結論を出すのではなく、2~3年よく考えてから」といった結論を先送りしたいという甘えです。既に6年間も教育に時間をかけてきて、他の学部出身者はもうプロとしての第一歩を歩みだしているときに、「もう少し考えてから」というその悠長さは、滑稽ですらあります。では、なぜすぐに結論が出せないのでしょうか。それは医学教育の6年間の間に真剣に自分の将来について考えてこなかったからです。ではどうしたらいいのでしょうか。なるべく低学年のうちから、「自分は研究と臨床とどちらに進むべきか」という意識を持つこと、持たせることです。常々私が申しているように、医学部を卒業したら道は大きく二つに分かれているのです。「医学者」の道と「医療者」の道と。そのことに思いを寄せずに6年間過ごしてきてしまったために、いきなり選択を迫られて、「また後で」とモラトリアムになってしまっているのです。まあ九大医学部のほとんどの人が、道が二つに分かれていることさえ認識できずに卒業していく現状から見れば、まだ二つの道が見えている人は賢明な部類なのでしょう。しかしその他大勢の人も5~10年経ってから、実は卒業時に道が二本あったことに気が付いているのです。そして意外と多くの人が、「研究の道に進めば良かった」と後悔しているのです。実際、その思いが強くて30歳近くになって研究を志す人も中にはいますが、残念ながら手遅れと言わざるを得ません。
5. 「とりあえず2~3年研修医をしてから」の愚かな理由
研修医というのは、朝一番に行って、一通り患者さんの回診をしたあと、種々の伝票を書き、検査結果やカルテの整理、検査や手術への立ち会い、採血や点滴、アルバイト、カンファレンス発表の準備、等々夜遅くまで、時に食事をする暇もないほど忙しく働かなければなりません。全く初めての体験ばかりで、物事をじっくり考える暇もなく働き、「自分は一人の医師として頑張って働いている」という意識に充実感を覚えるかも知れません。でも、これは頭を空っぽにして働いている人が陥りやすい一種の自己陶酔であって、現実的には研修医は雑用係でしかありません。臨床医としての真の喜びは、知識と理論に裏付けされた診断及び治療方針に、自分の経験から来る匙加減を加えて、患者の自然治癒を助けることにあります。別に伝票を書いたり、採血をすること自体が喜びではないことは自明です。しかしそのような一人前の医師になるためには、研修医の後もずっと臨床医として経験を積まねばなりません。
雑用係をするために、2~3年の貴重な時間を潰すことは、全く愚かなことです。研修医とはテニスプレイヤーに例えれば、球拾いのようなものです。誰でも球拾いから始めることは仕方のないことですが、それは将来的にテニスの楽しさを満喫するためのものであって、球拾い自体が楽しいわけではありません。君達が野球選手を目指しているのに、「2~3年テニスもしてみたい」と言ってテニスコートで球拾いをしているようなものです。その間にも君達のライバルは野球の練習をしてどんどん野球がうまくなっていきます。そんな状況でも君達は球拾いをしたいと思いますか?
私達から見れば、2~3年研修医をすることは、2~3年海外旅行へ行って遊んでいるのと全く同じです。しかしやっかいなことは、海外旅行をして遊んでいるのに比べて、研修医をしていると何となく社会的に”働いている”と認知されてしまうことで、本人もそのように思い込んでしまいます。しかしながら上に述べた理由により、プロの研究者を目指す人間としては、遊んでいるのと何ら変わりはないのです。
6. 2~3年研修医をしたらどうなるか
私の経験から言って、「とりあえず2~3年研修医をしてから、基礎研究にいくかどうか考えてみたい」と言って研修医になって、実際に基礎に帰ってきた人は皆無です。それは何故でしょうか?甘やかされてしまって闘争心を失ってしまうからです。研究というのは世界を相手にした闘いです。それはやりがいがあり、一生を賭けるに値するだけのものがあります。しかしその世界に飛び込むためには、ある程度の勇気が必要なことも事実です。「えいっ」と決めてしまう若さが大切で、迷った挙げ句に一度猶予期間をおいてしまうと、もうその勇気が出てこなくなります。
さきほど、2~3年研修医をすることは、2~3年海外旅行へ行って遊んでいるのと全く同じと言いましたが、笹月教授の言を借りれば「遊んでいるよりたちが悪い」とのことです。研修医はその実態は雑用係以外の何者でもありませんが、社会は一応一人前の医者として扱ってくれます。看護婦さんや患者さんからは「先生」とチヤホヤされて、何となく偉くなったような気がします。しかしその反面では、それが単に外見的なものに過ぎないこともよく自覚しているのです。そのような見せかけのプライドの生活を2~3年もすると、実の世界の人達に対して恐れを抱くようになり、そのような虚のない世界に入ることが億劫になってきます。ですから、このような人が再び帰ってくることはまずないのです。
7. 基礎研究者として花が咲かなければ臨床に行くことは可能
臨床と一口に言ってもいろいろな人がおり、それぞれに違う目標を持っています。臨床はそれが許される世界で、個々の目標により自分の生き様を選べます。一度社会人として働いていた人、多浪して大学へ入ってきた人、病気で長く休学してしまった人、等でも受け入れてくれます。基礎研究を目指して挫折した人でも、臨床医として再びチャレンジする人はいます。つまり、どうしても迷いがあるとか、結論を先送りにしなければならないのならば「とりあえず2~3年研修医をしてから、基礎研究にいくかどうか考えてみたい」のではなくて、「とりあえず2~3年基礎研究をしてから、臨床にいくかどうか考えてみたい」というオプションの方が現実的です。2~3年の基礎研究は、その後の臨床研究に役立つことがきっとありますが、2~3年の研修医体験は研究には何の役にも立ちません。
8. まとめ
- 臨床を2~3年してから、基礎研究をするのは最低の選択である。
- サイエンスの世界は猛烈な勢いで進んでおり、2~3年も遊んでいる場合ではない。
- 医学部出身者は他の学部出身者に比べて既に3年遅れている。
- 研修医を2~3年やることに合理性はない。
- 研修医を2~3年したい、という最大の理由は決断を先延ばしにしたいという甘えである。
- 一度研修医を2~3年したら、再び基礎研究に帰ってくることはない。
- 本当にプロの研究者を目指すなら、卒後すぐに研究を始めよう。
No. 4 よくある質問3 – 臨床と基礎研究のそれぞれの良さとは?
1. どちらも素晴らしい、しかし一つしか選べない
私は半年弱の臨床経験しかありませんが、物事の本質(だけ)を見極めるなら、それでも十分な時間でしょう。その前提に立って、言わせていただければ、結論は「どちらも一生を賭けるに値する素晴らしい職業である」けれども、「どちらか一方しか選ぶことができない」ということです。そして人それぞれに適性があって、基礎研究に向いている人、臨床医療に向いている人がいます。それぞれの良さ(悪さ)とは一体何でしょうか?君達の頭の中で、このポイントがはっきりしていないので、将来の選択を思い悩む(又は、全く考えることなしに大勢に従って臨床へ行ってしまう)のです。しかし、そのような指導をしてくれる教官がほとんどいないのが、日本の医学部の現状ですから、君達だけに非があるのではありません。むしろ、日本中の基礎医学研究者がいかに未来の医学に対する投資を疎かにしているか、その怠慢さが責められるべきであると考えます。責任論はさておき、この点に関するポイントを私なりに整理してみました。
2. 臨床の本質は奉仕である
臨床の最も大切な社会的使命は、言うまでもなく病気で苦しむ人々を救うことにあります。残念ながら、臨床医に創造性はあまり必要ではありません。下手な創造力はかえって危険ですらあります。例えば、普通には認められていないような薬を投与したりする内科医や、自分の思い付きで術式を変えてみたりしたがる外科医には、君達も診て欲しくないでしょう?このようなことは一種の人体実験であって、通常では行ってはならないものです。実際に臨床の現場では、かなりの事項がマニュアル化されています。高い知能を持った人が、創造性の許されない職場にいることは、大変辛いことです。それでは、何が彼らを突き動かしているのでしょうか?私には、彼らの大多数にとって報酬とか名誉とかは、最も大切なファクターではないように感じられます。最も大切なことは、自分で自分の人生に満足できるかどうか、その一点にかかっているのではないでしょうか?臨床医にとって最大の喜びは、自分の患者が元気になって、明るい笑顔を取り戻すことであることは、疑いないことであると感じます。それは患者やその家族から感謝されたい、といった俗な精神ではありません。自分が人の役に立ったという満足感なのです。そして、それは奉仕の精神と共通するものがある(というか、ズバリそのもの)と言えます。医療とは人(人類)のための奉仕であるということは、ヒポクラテスの時代から変わらぬ真理です。
3. 基礎医学の本質は創造である
基礎研究においては、他人と同じことをしても全く評価されません。そこには自分なりのテーマ、自分なりの発見が必要で、創造性が最も重要なファクターになります。知能の高い人達にとっては、創造性を発揮して新しい発見をするということは、報酬・名誉・権力といった俗界を超越した、もの凄い喜びがあります。暗室で一人ガッツポーズをしたことも数知れずです(涙したことも同じくらいありますが・・・)。思いがけず大発見をした日は、朝まで興奮で寝られないこともありますし、人によっては興奮のあまり、街を徘徊してしまうこともあるようです(笑)。正直言って、それが人の役に立とうが立つまいが、そんなことはどうでもいいのです。真理の解明、という最も知的好奇心を刺激する美酒に酔いたい、というのが本心です。サイエンスというのは本来そういうもので、「○○病の治療に役立つから」「××症の診断に応用できそうだから」という近視眼的な目的のためにやっているのではないのです。しかし、結果として、それが世のため人のためになればそれでいい、と私は考えていますし、そのくらいの気持ちでなければ大きな社会的貢献につながるような本質的な発見はできないだろうという気合いで研究をしています。そして、基礎研究の社会的な貢献というものは、20~30年後に初めてわかるのであって、現在の我が国のように目先の実利だけを求めたり、判定したりする科学政策は、全く的が外れていて、本当に行く末が心配になります。
4. 臨床医の苦しみはベクトルのズレにある
大学で臨床を行っている医師は、非常に多忙です。何故なら、彼らには「教育・研究・診療」という3つの業務をこなさなければならないからです。多くの場合、時間(現実)の上では診療>>研究>教育であるけれども、本人の意識(情熱)では、研究>診療>>教育の順番であるようです。この現実と情熱の解離が大学病院医師を苦しめ、ダメにしています。どちらにしろ、君達の教育は一番下に位置しているのは事実です(笑)。本来の大学医学部の使命は、教育が最も上位にこなければなりませんが、それも致し方ありません。というのも、現在の大学病院医師の評価システムに、教育というものはほとんど重視されないからです。逆に、研究が評価の大きなファクターとなっています。しかし上に述べたように臨床の最も大切な社会的使命は、言うまでもなく病気の人間を救うことにあり、現実的にそれを無視することができないので、上記のような現実と情熱の解離が発生するのです。言い換えれば、社会的使命(診療)と個人レベルの興味(研究)のベクトルの方向がズレているのです。
5. 臨床医も本当は研究がしたい
通常、真面目に診療に取り組んでいる医師が研究に割くことのできる時間は、本当に少ないようです。週に1~2日あれば良い方です(それ以上している人は臨床医という名の基礎研究者です)。また、実験をしているときに自分の受け持ちの患者が急変すれば、その実験を放棄しなければならないこともあるでしょう。そんな限定された時間でできる研究には、やはり限界があります。どうしてもレベルの低い、他人の研究の焼き直し的なものになってしまうのは避けられません。私達はそういう研究を称して、「鉄銅実験」と嗤っています。鉄でこうだったから、次は銅でやってみましょう、的なもので、このような研究は単に論文のための研究でしかありません。そしてその論文は本人の業績という以外の何の価値も持たないものが大部分です。臨床の大学院生の学位論文審査をしていると、そのような類の論文のあまりの多さに驚きます。しかし本来は頭の良い人の集団ですから、やはり自分の実力を試してみたくなるときがやってきます。真の研究をしてみたい、という強い衝動に駆られるときが、臨床医になって5、6年すると起こるようです。そこで基礎研究者に転向する人もごく少数ながら存在しますが、大部分の人はそのようなフラストレーションを抱えながら、診療と研究の間で悩み、苦しんで、諦めていく、という経過を辿るようです。私の知り合いの臨床医には、本当に頭が良く、人間的にも誠実で、立派な医師が数多くいます。彼らは一様に「あと10歳若かったら、自分も基礎研究へ転向したかも知れない」と言います。そして全ての時間を研究に打ち込むことのできる環境を羨ましがります。彼らのような優秀な人達が大挙して基礎研究に押し寄せてきたら、私は困りますが・・・幸い現在のところ、それはないようです。
6. 評価が単純明快なのが基礎研究のいいところ
基礎研究者は好きな時間に来て、好きなだけ研究をして、好きな時間に帰ります。大きな声では言えませんが、一日3時間しか働かなくても、人が唸るような業績をあげれば誰も文句を言いません。「結果が全て」のこの世界のルールは単純明快で、臨床のようなベクトルのずれはありません。また最近ではインパクト・ファクターという論文の引用率を定量化したものがあって、論文の重要性が数字で表せるようになってきました。インパクト・ファクターで研究の質を推し量ることについては賛否両論がありますが、私は評価を単純にすることができ、それほど実体と大きなズレがないと思っていますので、基本的に賛成です。原則的には、最も価値の高い論文は当然Nature, Cell, Scienceといった国際誌に掲載される可能性が大です。もちろん良い論文が評価の高い科学誌にでないというケース(やその逆)もままありますが、それでも論文の質とインパクト・ファクターには高い相関があると思っています。もちろん相関係数は1にはなりません。インパクト・ファクター反対論者は、その相関が絶対でないことを挙げますが、本来評価の基準に絶対というものはあり得ず、あくまで実体と高い相関を示す価値基準を採用するのだという原則を彼らは無視しています。
7. 絵描きと似顔絵描きの違い
しかし、基礎研究の世界において、評価が単純明快であるということは、必ずしもいいことだけではありません。まず誤魔化しがききません。努力しても報われないことだってあります。学歴や過去の実績が何の役にも立ちません。つまり実力が全ての厳しい世界である、と言っても過言ではありません。その点ではプロスポーツや芸術家と良く似ています。例えて言えば、基礎研究者は一見わけのわからない抽象画を描いている絵描きと一緒です。そこに模倣はありません。独自の創造性とその内容が評価される世界です。絵が売れなければ食うにも困ります。しかし一発当てれば後生にまで残る作品と名声が得られます。それに対して臨床医は似顔絵描きです。創造力に富んだ絵は困ります(街角でピカソの泣く女のような似顔絵を描かれから困るでしょう?)。模倣が大切です。しかし確実に収入は得られます。でも、似顔絵描きだって、本当は自分のオリジナリティーを大切にした普通の絵を描きたいのです。君達、短い、一度きりの人生です。本当の絵を描いてみませんか?
8. 二兎を追うものは一兎をも得ず
初めに言ったように、臨床も基礎研究もどちらも打ち込めば素晴らしい世界です。しかし、他の稿でも書いたように、どちらかに打ち込まなければ、中途半端な人生で終わってしまいます。私個人はもう一度生まれ変わったら、今度は臨床医になってみたいと思っています。私は昨年、母を乳癌で亡くしました。3年にわたる長い闘病でした。九大の第一外科には本当にお世話になりました。そしていろいろな先生方にお世話になり、彼らが患者を第一に考えてくれる本当の医師であることを肌で実感しました。そのときの私はただの患者の家族でした。手を合わせて拝みたい気持ちでした。一人でも多くの人に、そういう安らぎを与えてあげたい、そういう人生も悪くないな、と思います。ですが、残念ながら人生は一度きりです。自分の可能性を試してみたい、自分の知的好奇心の赴くままに生きてみたい、という我が儘な心を抑えることができません。科学者とは本来我が儘なものです。母はそんな息子の我が儘を許してくれるでしょうか。
9. まとめ
- 臨床も基礎研究もどちらも素晴らしいが、両方はできない。
- 臨床の本質は人の幸福を願う崇高な精神に拠っている。
- 臨床の現場では創造性を発揮することは許されない。
- 基礎研究の本質は創造性にあり、それは人間本来の欲求でもある。
- 臨床医は現実の義務と個人の欲求との間に深刻なズレがある。
- 基礎研究者の評価は単純明快で爽やかだが、それだけに厳しい面もある。
- 二兎を追うものは一兎をも得ず。
No. 5 よくある質問4 – 家庭と研究の両立は可能ですか?
1. 一通のメール
最近、ある学生さんから次のようなメールを戴きました。(中略)「もちろん、そういう考え(家庭を顧みない方が研究者として成功する)のほうが、研究で成功する確率が高くなるとは思いますけれど、研究というのは、必ずしも努力が結果に結びつかない分野だと思うので、何も犠牲にしないからといって、成功する確率がそれほど下がるとは思えないのです。犠牲にするのは、一定の、お金と時間だけでよいと思っています。虫が良すぎるでしょうか?」。敢えて極論すると、「はい、虫が良すぎます」と答えざるを得ません。
2. 努力したヤツが勝つのは当たり前
どんな研究者も人生の100%を研究に投入できる人はいません。しかし、30%の人、50%の人、80%の人とバリエーションがあるのは確かです。「研究というのは、必ずしも努力が結果に結びつかない分野だ」というのは、大局的に見れば間違っています。「大局的」と言ったのは、個々の例を見れば、たまにはあまり努力しなくても成功した人や、凄まじい努力をしているにも関わらず、まったく業績がでない人がいるということです。しかし、例数を増やせば、研究の世界では努力と結果の間に明白な正の相関関係があるのは厳然たる事実です。
科学において(というか競争的な職業全ては)結果=才能 × 努力です。よく学生への例え話に使うのですが、科学は福引きのようなもので、赤い玉がでることが成功、白い玉は不成功とすると、才能=「赤い玉が含まれている確率」で、努力=「回す回数」です。しかし、才能が同じならば、より多く回した方が、赤い玉が出る確率が高いに決まっています。個々の例を見れば、赤い玉が1000個に1つでも、1度目で赤い玉を出す人もいるでしょうし、1000個に500個くらい赤い玉が含まれているにも関わらず、何回やっても出ない人もいるでしょう。でも、例数を増やして客観的に眺めるとき、これらの例外は希釈され、多く回したヤツ(つまりより努力したヤツ)が勝つ、という一般論が導けることは明白です。
3. 家庭型サイエンティストにも二通りある
科学者には家庭を大切にするタイプと家庭を顧みないタイプがいます。私の知り合いでも、家庭を大切にするタイプの研究者がかなりいます。そのうち8割は科学者として競争的な仕事をするのに不適格です。しかし残りの2割は、家庭を顧みないタイプの研究者と互角に仕事をしています。何が異なるのでしょうか?最大の違いは、ダメグループは「仕事も大切だが、家庭も大切である」という論理を基に自分自身に言い訳を作っています。自分に言い訳ができると、人間弱いもので、低い方へどんどん流されて行きます。
良い方のグループは、自分がハンデを負っていることを十分理解しています。重い荷物を背負ってマラソンをして、さらに何も背負っていない奴に勝たなければならない、という覚悟があります。このタイプは、限られた時間の中でものすごく集中して仕事をこなします。そしてどうしても必要な場合は、ある程度家庭を犠牲にする柔軟性も持ち合わせています。こういうタイプの人は、ある程度時間をやれば着実に結果を出していきます。
4. 人生の成功って何だろう?
科学は競争ですから、なるべく有利な条件で闘うヤツが勝つ確率が高いのは、ある意味当たり前です。ここで整理して考えたいのは、「研究生活で勝つことが果たして幸せな人生かどうか?」、です。ここには多種多様な考え方があり、「幸福とは何か」という哲学の最大の命題にぶち当たります。実は私もそう言われると迷ってしまいます。
しかし、観念論を捨てて経験論から物事を見たとき、私は「研究生活で勝つことが幸せな人生だ」と確信せざるを得ません。家庭を研究より上位に位置づける人は、仕事での評価は低くなり、社会的な地位も低いままで、人間としてのプライドがどんどん矮小化してきて、脹らみのない男(女性の方、ごめんなさい)になってしまうと思うからです。古い考えかも知れませんが、男は仕事が出来てナンボだと思いますし、そういう男でないと女性にもモテませんし、そういう男に惚れる女性でなければ人生を共有するに値する相手ではないです(笑)。
特に研究者として一人前になる前に、「家庭が・・・」という人は、問題があります。家庭が幸せになるためには、まず自分が仕事人としてしっかりした社会基盤を持つことが何よりも重要です。そのためには、ある一定時期、家庭を顧みずに働くことも必要でしょう。逆説的ですが、「家庭を顧みないこと」が結局は将来的に「家庭の幸せ」につながると私は思います。そしてそれを理解できないか、または実践できない人が沈んでいくのだと、そういう例をまのあたりにする度に、感じています。
5. 所詮全ては得られない
とにかく私のアドバイスは、「自分に言い訳をするな」ということです。競争社会は君達の個人的な都合なんか、全く顧みてくれません。それを自覚するものだけに、成功は訪れます。家庭を大切にすること自体は決して悪いことではありませんし、それが人生における幸福の大きなファクターであることは間違いありません。しかし、そのために沈んでいく多くの人を目の前でいつも見ているので、そうならないように君たちには是非とも一言忠告したいです。
私が好きな言葉に次のようなものがあります。
You can’t have everything.
長々書いてきましたが、とどのつまり言いたいことはこれだけです。
6. まとめ
- 努力と結果は、大局的に見れば正の相関関係にある。
- 家庭型サイエンティストの8割は結局人生においても敗者になってしまう。
- 自分に言い訳を持った時点で、低い方に流されていく。
- 家庭を大切にしながら科学をすることは人一倍の努力が必要。
- 全てで成功しようと考えるのは、虫が良すぎる。
No. 6 よくある質問5 – 科学は競争か?
1. 最も多い批判
本HPも最近読者が増えてきたようで、各地へセミナーに行くと、必ず「HP読んでいます」と声をかけられるようになりました。この文章は元々九大医学部の学生に向けて書いたものですが、共感して下さる方は九大医学部生よりも、私と同じ立場にある他大学の教官の方が多いようです。最近多忙にかこつけてなかなか更新できずにいましたが、年賀状に更新を求めるお手紙が何通かあったことから、もう少し頻繁に更新しようと考えています(笑)。
さて、このHPの読者が増えるに従い、いろいろなご批判のメールを戴くことも増えてきました。それもほとんどがある一点に関するご意見です。それは前回「家庭との両立は可能か?」の中でほとんど無意識に書いた一文「科学は競争ですから・・・」についてです。批判の内容は、「科学とは競争ではなく、未知の現象を解明したいという自己の欲求を追求するものである」「科学を個人的な競争や栄達のためにすることはけしからん。科学は社会の利益に還元されるべきものだ」というものが大部分でした。
私のいう「競争」とは、誰でも思い付く実験を誰よりも早くやる(クローニング競争とかノックアウト競争とか)という意味で使ったのではなく(時にはそういう実験も必要ですが)、他人よりいかに独創的で、科学界から認められるような仕事を、人より早く、多く、抜きん出てするか、という意味で用いたものです。それをご了解の上でお読み下さい。
2. 理想的科学者 vs. 現実的科学者
さて、無意識に「科学は競争ですから・・・」と書いてしまった私は、このリアクションを見て、なるほどと思いました。それは私がいつも抱えている「科学者とは何か」という疑問と全く一致するからです。私はその答えを見つけるべくいつも思い悩んでいるのですが、皆そうなのだなと。つまり多くの人(私も含めて)の頭にある理想の科学者像というのは、世間の流行など関係なく、自分自身の独創性の下に発見した生命現象について、世間の評価とは関係なく長年それについて独自の研究を重ね、ついには誰もが考えつかなかった大いなる理論の確立に至る、という求道者のようなもので、それに比して現在の多くの科学者は、世間の流行に流され、Cell・Nature・Science誌に論文を載せることだけを目標とし、Impact factorにしか興味がなく、周りの研究者との競争に明け暮れている、という俗悪な存在でしかないと。科学者は「科学が好きだから」科学をすべきであり、競争のために科学をすべきではない、というのが多くのご批判の趣旨でした。科学者はどちらであるべきなのでしょうか?前者を理想的科学者、後者を現実的科学者と定義して以下の議論をしたいと思います。
理想的科学者の方が、できればいいに決まっていますが、当然の疑問としては、「独自」の研究が果たして本当に「価値のある」研究なのか、という点があります。単に自己満足ではないのか?他人が興味を示さないような重箱の隅をつついているだけなのではないか?と訊かれるでしょう。私は「社会のために研究をしている」というのは誤りだと思っていますので、どんな自己満足的な研究をしても構わないと思いますが、やはり最終的には世間から評価されるような「なるほど」と思わせるような研究をしたいと思っています。
理想的科学者は世間の評価を気にしない、ということは現実的に研究費が取れないという問題点に突き当たります。鉛筆と紙だけで研究できる時代ではないのですから、評価を得ない限り研究の長期間にわたる継続は困難でしょう。つまり私達は、ホームランも狙いつつ、ある程度の打率を残さなければ一軍には残れない、というジレンマを抱えているのです。どちらがいいということではなく、理想を目指しつつも現実も疎かにしないのが、大人の対応というやつでしょうか(笑)。
3. 創造は評価と共にある
「科学が好きだから」「真実を知りたいと願う欲求は科学の本質」ということはごもっともですし、私も同感です。しかし、それだけではないこともまた真実です。よく私が使う例えに、科学者は芸術家のようなもの、またはプロスポーツ選手のようなもの、というのがあります。絵描きは絵を描くのが好きなのです。しかしながら、もしそれだけなら、自宅でコツコツ絵を描いていて毎日それを眺めていればいいでしょう。野球が好きなら裏庭でキャッチボールをしていればいいではないですか。でも絵描きであれ、作曲家であれ、自分の作品を世に問い、その価値を認めてもらおうとすることはごく自然の感情であり、私達はそれに対して特に違和感を覚えません。プロ野球選手が巨人に入りたがるのも、理解できますね。サイエンティストも同じです。人間の創造活動というのは、世の評価と表裏一体のものなのです。だから「好きだから」だけではアマチュアというか、それ以前の問題のような気がするのです。
4. 「科学は競争ではない」のウソ
私を含め、多くの現役サイエンティストなら誰でも「科学は競争ではない」と言われると苦笑してしまうでしょう。ある著名な科学者の言葉ですが、「大発見をしたその翌日から競争になる」そうです。好むと好まざるとに関わらず、私達の世界では競争の中に生きることは止むを得ません。常に大発見ばかりできる人ならば別ですが、私のように悩める科学者の多くはそうではありません。ノーベル賞を受賞した小柴博士は、アメリカで同様のニュートリノ検出器を作っていたのを知っていたそうですが、その競争に勝って今の栄光を手にされました。このようなことは生物学でも枚挙に暇がありません。競争は必然であり、避けては通れないものであり、ときには好んですることもあるものなのです。
5. CNSを目指して何が悪い?
誤解のないように言っておきますが、私は独創的な仕事を否定しているのはないし、他人の研究の二番煎じのような実験を推奨しているわけではありません。多くの臨床医がやっているような、肺癌ではこうだから、肝癌ではどうか?食道癌ではどうか?なんていう論文にはウンザリしています(医学部の学位論文は80%くらいこんなのです)。研究としては独創的でなければ意味がないと思っています。しかしパラダイムを打ち立てるようなマイルストーン的研究はなかなか難しいと実感しています。過去のそのような素晴らしい研究を見ると、幸運に恵まれなければできないことも多いと思います。しかし、「幸運は準備されたところに来る」といいますから、やはりしっかりした実力を持って常に独創的な研究をしたいと思っています。そしてそのような研究をしていれば、結果的にいい雑誌に掲載される機会も増えるでしょう。皆がそう思っている雑誌は当然人気が集まりますが、掲載できる論文数には限りがありますから必然的に競争になりますね。よく読まれる雑誌は引用される機会も増え、Impact factorも高くなるのはしょうがありません。私は内心「俗な表現だな」と思いつつも、誤解を覚悟で「Cell・Nature・Science以外は論文ではない」と若い人を鼓舞しています。昔は本当にそう思っていました(笑)。当時(ポスドク)のときは米国の一流研究室にいたこともあり、少なくとも一年に一報はラボからCell・Nature・Scienceが出ていたので、ラボで一番いい仕事をすれば、そのようなジャーナルに出せるものだと思っていました。今では、「多くの人に感動を持って読まれるような良い論文を書け」というつもりでそう言っています。では、そう言えばいいのに、という人もいますが、目標は端的で、かつ明確な方がいいのです。若い人たち、Cell・Nature・Science目指して頑張りましょう!
6. 日教組教育の弊害
科学にとどまらず、多くの創造性の要求される仕事には、非常に過酷な競争が必然的に存在します。それは「人・社会に認められたい」という人間本来の共通の欲求があるからかです。その欲求を否定すれば、今の科学・芸術・スポーツその他多くの文化はあり得なかったでしょう。社会主義の崩壊が持つ最も大きな教訓は、まさにこのことでした。しかしながら、私に「科学が競争とはけしからん」とメールを送ってきてくれた人たちから共通して受ける印象というか臭いは、「競争」=「悪」という単純な図式のインプリンティングです。もちろん初めに述べたように、創造性のない競争は悪いものです。そう思っているので、私は初め大学院教授会で一人だけ、その手の論文には「否」を入れていました(いつも49対1程度だったですが)。しかし、競争を否定するような間違った教育は、誰がどうやって導入したのでしょう?最近の若い人達には、特にいい意味での「競争心」が足りないように思うのは私だけでしょうか?戦後50年のいわゆる日教組教育はいろいろな意味で間違っていたと思いますが、「競争の否定」ほど困ったものはありません。最近は「ゆとりの教育」で円周率が3になったと言いますが、私達は3.14という変な数字だからこそ、実はもっともっと割り切れないものがあるのではないかと想像するのではないでしょうか?才子異国に婿。全くこの国の教育方針には辟易することが少なくありませんね。
7. まとめ
- 競争は独創性のぶつかり合いである。
- 世間の評価から解き放たれた科学者は理想だが、現実的には存在し得ない。
- 文化的創造は全て世の評価を受けて存在する。
- 多くの人に感動を持って読まれるような良い論文を書くべし。
- 競争=悪の呪縛から逃れよう。

「幻の原稿」編 『Q&Aで答える 基礎研究のススメ』

バイオ研究者が生き抜くための十二の智慧
目 次
- はじめに(中山 敬一)
- 第1章 ラボノートの書き方(水島 昇)
- 第2章 試薬・実験データの管理(鍔田 武志)
- 第3章 書類整理術(佐谷 秀行)
- 第4章 EndNoteを活用した文書作成術(中山 敬一)
- 第5章 マテリアルリクエストへの対応(水島 昇)
- 第6章 論文レフェリーコメントと闘う心構え(仲野 徹)
- 第7章 論文レフェリーをこなす(中山 敬一)
- 第8章 オーサーシップ(水島 昇)
- 第9章 Skypeでラボミーティング(上野 直人)
- 第10章 Journal Club(中山 啓子)
- 第11章 メディアを介した研究成果の発信(東原 和成)
- 第12章 プレスリリースの書き方(小泉 周)
- 番外編(1)ベンチワークの匠:ヒト型ロボット研究員『まほろ』(夏目 徹)
- 番外編(2)マウス系統の寄託と提供(理研BRC編)(吉木 淳)
- 番外編(3)バイオラボ秘書の仕事術(櫻井 紘子)
「雑用が多すぎる」。研究室の主宰者(PI)の間では、ほとんど挨拶代わりに使われる言葉です。君達のラボのPIも、いつもそうやってブツブツ文句を言っていることでしょう。では「雑用」とは何でしょうか?もちろん厳格な定義はないのですが、私の印象では、直接の研究活動以外のことは全て雑用にあたるみたいです。例えば、毎年度初めに書かなくてはならない大量の報告書とか(誰が読むのだろう?と思います)、他の研究者からの試料リクエストへの対応、他人の論文の査読、など多くの雑用がPIの時間を奪っていきます。自分の研究とは直接関係のないことに多くの時間を取られるのは本当にストレスですが、ラボのマネージメントをする限り、非常に多くの雑用をこなさなくてはならないのは、PIの宿命なのです。
ところが世の中には、このような雑用を簡単に片付けるためのノウハウを持ったスマートなPIがたくさんいます。つまり現場の知恵です。ところが残念なことに、このような素晴らしいノウハウは多くの場合、蓄積されたり伝承されたりすることなく、その人個人の一代限りの知恵として、終わってしまうことがほとんどです。大変もったいないことだと思いませんか?
本書の企画意図は、まさにここにあります。つまり多くのPI達が有する個人的なノウハウを多くの研究者に伝え広め、雑用に取られる時間の総量を大幅に削減することによって、日本の科学の質と量を高めようというのです。本連載が、現在PIである人だけでなく、将来PIになる人にとっても有用でありたいと願っています。今回はとりあえず私の身の回りの方々の中で素晴らしいノウハウを持った人の秘伝を紹介してもらいますが、日本には他にもこのような秘伝が数多く存在することでしょう。本書が試金石となって、いずれは、数多くの情報が統合され広く交換されるよう、心から期待しています。
2013年8月
中山 敬一

君たちに伝えたい3つのこと
目 次
- 目 次
- アムロの悲劇とシャアの悲劇—後悔のない人生を送るために(序章より)
- クリエーターには二つの大きな喜びがある(第1章より)
- 「ハイリスクハイリターン」仕事の、リスクを大きく減らす方法(第2章より)
- 感情が硬直化する前に決断するのが大切(第3章より)
- クリエーターは、突飛なことを思い付く人ではない(第4章より)
- プレゼンを究める方法(1) ストーリーは単純に(第5章より)
- 早すぎる独立は悲惨な結果を招く(第6章より)
- 女性研究者の有利と不利(第7章より)
(その他、具体的で本質的なアドバイスが満載!)
全93項目
当HP内に掲載の「教授からのメッセージ 〜 幻の原稿」は元々、某科学専門誌に掲載される予定でしたが、「内容が過激すぎる」という理由で発刊直前になって急遽ボツになった曰く付きの文章です。内容は3分の1くらい執筆しておりましたが、残りは未完でした。
なぜ「内容が過激」とされたのでしょうか?それは本質を正直に晒しているからです。人間は感情の生き物ですから、本質を直視できない人も多くいます。しかしそうやって本質を隠していると若い人に誤ったメッセージを与えることにもなります。人生を左右する決断に際して、一つくらい本音を晒して若者を啓発する本があってもいいのではないでしょうか?
5年間にわたり多くのWEB読者の声に支えられ、やっと残り3分の2を執筆し、さらに既公開の部分も抜本的に書き直して、このたびビジネス書を多く出版しているダイヤモンド社から「完全版」として出版することになりました。
書き直しにあたっては、医学生だけでなく、文系・理系問わず読めるように、大幅に書き直しました。またHPの予告にはなかった「文系ビジネスパーソンにも役立つ、研究者の仕事術」や「クリエーターも必要不可欠、コミュニケーション力の身につけ方」などの章も追加して、WEBを既に読まれた方も全く違う観点から楽しめるようにした本です。
是非手にとって読んでみて下さい。あなたの人生の決断の一助になれば幸いです。
2010年7月
著者

中山敬一が語るジェンダー論
はじめに
10年前に出版した著書の内容について、不幸な誤解により、図らずもご不快な思いをさせてしまった方にお詫び申し上げます。
Abstract
私が10年前に書いた「結婚は△、出産は×」という文章が誤解されたまま一人歩きしているらしい。しかし、これは現代日本が「結婚は△、出産は×」という悲惨な実情にあることを端的に表現したもので、私の個人的な思想ではない。むしろ私はこれらの現状を深く憂いており、女性のキャリア形成を応援したいと思っている。しかし、世界一流の科学者を目指すためには、夫婦どちらかが一定の犠牲を払うことが避けられない現状となってしまっている。それが女性である必要は無いにも関わらず、結局は女性が損をするのが現代日本社会の悪弊である。そういう現状をしっかり見据えつつも、何とか解決する方法を皆で考えていきたい。
Introduction
今から約10年前(2010年)に『君たちに伝えたい三つのこと − 仕事と人生について 科学者からのメッセージ −』という一冊の本を上梓した。その中の一章に「結婚は△、出産は×」と銘打った章がある。この章は当研究室のウェブ上にて無料で読めるので、是非ともご一読願いたい。
10年前には、その一文を問題視するような社会的風潮はあまりなかった。しかしそれから時代は徐々に変質し、私の伝えたいことが正確に伝わらず、「中山 敬一は女性差別論者でけしからん」という方々が増え、中には苦情の電話が大学まで来たこともある。このことは、社会がこの問題に真摯に向き合うようになってきたことを示しており、喜ぶべきことなのかもしれない。
私は従来、研究以外の意見に関しては無言を貫くことをポリシーにしてきたが、ふと別の考えが頭をもたげてきた。不本意ながらも不快な気持ちにさせてしまった方々に申し訳ないが、幸か不幸か、議論の場が与えられたわけで、これを機会に「中山 敬一が考えるジェンダー論」を述べることにしたい。これが導火線になって広く議論が巻き起こり、日本社会の後進性が少しでも改善されれば、私の悪名も少しは世の中の役に立つことであろう。
本文
1. 「結婚は△、出産は×」の真意
私の本をきちんと読めば明白であるが、私自身が「結婚は△、出産は×」と考えている訳ではない。むしろ逆である。私は、そのキャリアを応援したいと真摯に考えている。
事実、私の研究室では多くの女性が(楽しく???)働いており、中には二人の子供を出産し、育児をしながら、世界一流の研究に励んでいる女性研究者もいる。過去には女性の助教や准教授が在籍していたこともあるし、その中から二名の女性教授を輩出した。この点を鑑みて、私が女性のキャリア形成を否定したり、阻害したりするような人間ではないことを理解して頂きたい。
また私のパートナーが研究者なので、普段から女性研究者の率直な意見を聞く機会に恵まれている。男性の視点では気が付かないことも多々あるし、想像していたことと正反対のこともよくあるのだ。私は女性を積極的に採用したいと思っているし、研究者における男女比は1:1でいいと考えている。
2. 厳しい競争社会に生きる科学者達
研究で世界一流を目指すということは、いわばオリンピックで金メダルを狙うことと同じである。金メダルを史上最も多く獲得している水泳のマイケル・フェルプスは、4年間で練習を休んだ日は0だと言う。ゆっくり休んでいるオリンピック選手などいないように、のんびり研究をやっている一流の研究者など寡聞にして知らない。
どんな世界においても、超一流を目指すものは、男も女も関係なく、血反吐を吐くような思いで仕事に打ち込んでいるものだ。
3. 現代日本社会の実情
日本社会の後進性が、このような厳しい現状の中で、女性の進出を大きく阻んでいる。
妊娠は心身共に大変な負担を女性に強いるが、それを男性が肩代わりすることは不可能である。育児については男女平等に負担することは、机上では可能だが、女性側に負担がかかっているのが現状である。積極的に男性が時間を割くなど、女性の負担を軽減する方法はいくらでもあるはずだ。
拙著を執筆してから10年の歳月が経ち、日本の環境も次第に変わってきたと肌で感じる。しかしそれでも、2020年時点の我が国において、仕事を早退したり、急遽仕事を欠勤したりすることは、いまだになかなか困難な現場も多いだろう。例えば、従業員5名の会社で、決算期の直前に深夜まで残業しなくてはならない時に、保育園の出迎えで17時に帰宅する社員がいたら、周りの社員は徹夜になるかも知れない。例えば、多忙を極める病院の内科外来で担当医師が2名だった場合、その片方の子供が突然熱発したので出勤できないと外来開始直前に連絡があったとき、もう一人の医師の絶望感は想像するに余りある。
「もっと人数を増やせば良い」などというのは理想論に過ぎる。現実は、人数も予算もギリギリのところで皆何とかやりくりしているのだ。組織が大きいところでは、何とかやりくりすることも可能であろう。社員が1000人もいれば、数名が急に休んでも何とか対処できるかも知れない。しかし、上記の例のように、5名とか2名とかの場合は、そういうわけにはいかない。そして、われわれの研究室も同じような規模なのである。大学の教授とは、実態は零細企業のタコ社長のようなものだ。
4. なぜ女性だけなのか?
残念ながら、現代日本において、研究室の規模が小さく、夫婦共に深夜まで研究することはほぼ不可能である。そんなことをしたら、子供が死んでしまう。
そして今までは、常に女性が暗黙のうちに損な役回りを押し付けられてきた日本社会の現状を憂いて、10年前は出産は×と記した。しかし、私はこの古い風習に反対である。なぜ、女性だけなのだろう?男性がもっと育児を担当してもいいのではないか?現状では、子供を持つ夫婦両方がハードに働くことは、様々な条件に恵まれない限り、なかなか困難だ。
5. 現状は容認しないが把握は必要
ある研究者の方から、次のようなご意見をいただいた。「現状を容認することは差別の助長である」と。なるほど、これは私も頭から反対ではないし、そういう視点もあると思う。少なくとも、この方と私とは「女性の立場を改善しよう」という点では、同じ方向を向いていると感じる。
ただ、一点断っておきたいことがある。「容認」とは「これでいい」という意味だが、何度も繰り返し述べているように、私は「現状がこれでいい」とは一切考えていない。現状は良くないが、それはそれで実情を認識し、さらにそれを改善するために皆で努力していきたいと考えている。全ては正しい「現状把握」から始まるのだ。
科学者というのは、その職業の本質として、現状の問題点を洗い出し、それを様々な方向から議論し、考察する人種である。そこには前提もタブーもない。私は自由な議論がしたい。自由で真摯な意見の渙発によって、この良くない現状に一石を投じたいのだ。
6. 解決策は何か?
もちろん、雇用している女性が妊娠・出産したら(もしくはその夫が育児に参画するなら)、もう⼀名雇⽤してもいいというようなルールができれば、女性の雇用は増えるかも知れない。実際、JSTの研究費ではそのような制度が存在したことがある。政府や社会がすべきことは、まさにこういうインセンティブを与えることである。深夜まで使える託児所をたくさん作る、研究者をサポートする技術員や補佐員、コアラボの制度を充実させる、労働を代替えしてくれるロボットの導入を促進するなど、個人に負担のかかりすぎる労働集約的な環境を改善することも大切である。
このように解決の方法はいくらでもあるだろう。しかし、こういうことは、もちろんタダではできない。それなりの、いや、かなりの投資(税金)が必要である。しかし為政者は実はそこまで本気ではない。だから、結局やらないのだ。私もいつも良い方策を考えているのだが、なかなか現実的で即効性のある案を思い付かないのが口惜しい。
7. 皆さんのアイデアを募集します
皆さん、この問題に対する解決策を一緒に考えましょう。実効性のあるアイデアをお寄せいただければ、私が責任を持って、しかるべき組織へ働きかけます。妙案をお待ちしております。

生い立ち特集
DOCTOR’S MAGAZINE 7月号: No.68 July 2005 p21 掲載
株式会社 メディカル・プリンシプル社 (ホームページ URL https://www.doctor-agent.com/)
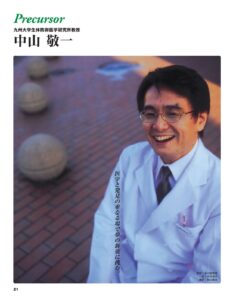


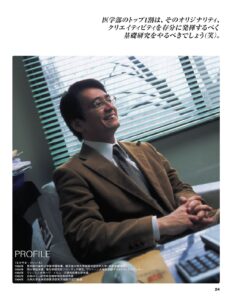

PDF 版(推奨)のダウンロードは、こちら から

教えて、先生!
Kyudai Walker No. 28(2011冬号)
HTML (TEXT) 版 – 教えて、先生!
PDF 版(推奨)のダウンロードは、こちら から